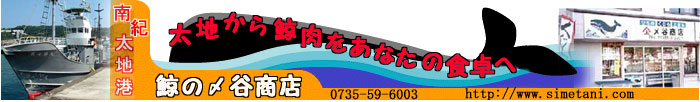

行灯型灯台が寛永十三年設置された、明治五年の廃止されるまでは
灯火は鯨油を使用し一夜に3合〜4合の油がつかわれたそうです。
手前の山見跡は古式捕鯨では山見で鯨を見つけ沖合いで。
待機している勢子船や地で待機している網船に
鯨の見えた方向を知らせるため狼煙をあげた当時灯明崎には
三ヶ所の狼煙場がありました。太地を発祥とする
古式捕鯨の史跡として重要です。

この山見番所は太地浦(太地町)の五ヶ所に建てられており
回遊する鯨の発見とその動きに注意し山見相互間の連絡と
海上の勢子船、網船に指令を与えるなど捕鯨を行う上で
最も重要な役目を果たしていました。
この山見群の総指揮者には、捕鯨にたずさわる一族の中でも
最も権威のある家筋の人でなければ
この重任にはつけなかったという。